ごちゃごちゃの世界をスッキリ整理する冴えたやり方
「世の中、複雑なことが多すぎる!」そんなふうに思っているあなたへ、この記事では身の回りの「複雑さ」を解消するコツをご紹介します。
日々の暮らしのあらゆる場面で「複雑さ」を感じることが増えているのは確かです。先が読めない国際情勢、個人間のコミュニケーションでもさまざまな価値観がぶつかり、デジタルデバイスも新機種が毎年登場。さらにSNSも加わって私たちはいつでもオンライン状態。誰も彼もが、膨大な情報を常に浴びていると言えます。
処理しきれない情報が溢れる中で人々が「もう無理!」と感じ、燃え尽き症候群のようになりかねないのも不思議ではありません。その対策のひとつとして登場したのが「マインドフルネス」。これは「本当に大事なこと」に意識を向ける方法です。例えばビジネスでは、すべての作業工程を細かく把握する必要はなく、それぞれの工程が日々の仕事にどんな意味を持つのかに集中すればいいのです。
この記事の本題はマインドフルネスについてではありません。でも、本当に大事なことに意識を向けるという考え方は、とても参考になります。
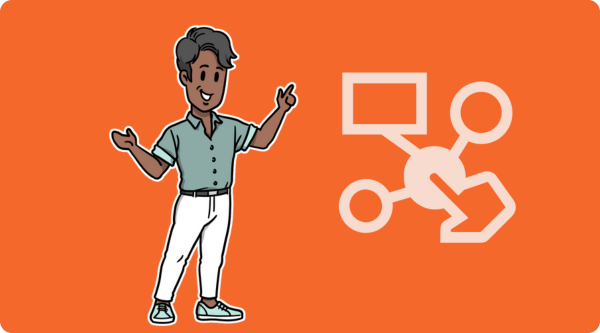
複雑に思えることが「本当に複雑」だとは限らない
多くの人は、物事が複雑なのは「その問題自体が難しいから」だと思いがち。でも実は、その複雑さは脳の処理方法によって発生していることが多いのです。
私たちの脳は非常に優秀で、大量の情報を処理して世界を理解できます。ただし「すぐに理解できる」量には限りがあります。混乱や難しさを感じるのは、多くの場合、私たちの情報処理・分析・理解の能力の限界によるものです。
例えば株式市場。株価は常に変動し、それに影響する要素も無数にあります。そのため、多くの人が市場を「非常に複雑」だと感じます。でも本当は、市場そのものが複雑なのではなく、「それらすべてを同時に理解する脳の能力」に限界があるから難しく見えているのです。このことを知っている投資家は、市場をより柔軟な考え方で見ることができ、投資判断の質を高め、ストレスを減らすことができます。
複雑に見えるのは、多くの場合において脳の処理のしかたの問題。そう理解すれば、仕事でも私生活でも、議論や問題にオープンかつ建設的に向き合うことが可能になります。加えて、自分や他人の限界を理解すれば、共感や忍耐力を育てることにもつながります。
世の中の「パターン」を見つけて複雑さを減らす
物事を分かりやすくするには、私たちの思考に「2つのモード」があることを知っておくと役立ちます。心理学者のダニエル・カーネマンは、これを「システム1」と「システム2」と呼びました。
システム1:素早く、自動的に判断するモード。本能的な反応に近い。
システム2:時間と労力を使い、じっくり考えるモード。批判的思考も伴う。
例えば、難しい数学の問題に出会った時に「面倒だな」と避けたくなるのはシステム1の反応です。一方、システム2を使えば、じっくりと考えて問題の中にあるパターンを見つけ、解答にたどり着くことができます。そして世界は、無数のパターンで成り立っているのです。例えば…
- 子どもの頃に学んだ「価値観」というパターン
- 毎日の「生活習慣」というパターン
- 仕事の場で守る「ルール」というパターン
注目すべきは、パターンの持つ「繰り返される」という特徴です。これが現実を整理して、よりシンプルに見せてくれます。世の中の「複雑さ」を減らす鍵が、ここにあるのです。
パターンを活用した動画で理解を深める
同じ出来事が何度も繰り返されるほど、それは単純に感じられます。これを動画制作に活用するのが「ストーリーテリング(物語で伝えること)」です。誰もがよく知る物語のパターンに当てはめることで、複雑なテーマを分かりやすく伝えることが可能になります。
例えば、何か問題が起き、解決策を得て、実際に問題を解決するという物語の流れは、多くの映像作品や、広告などでも共通してよく使われるパターン。こういったパターンがあるからこそ、アクション映画や恋愛ドラマの展開はだいたい予想できるわけです。
複雑に見える物語も、実は単純化されたパターンに沿っています。難しいトピックを扱う動画でも、要素を既存のパターンに沿ったフレームワークに組み込むことで、より理解しやすくなるのです。ストーリーテリングに加えて、イラストなどのビジュアルや、言葉も理解を助けます。

「ストーリーテリング」が複雑な情報を解きほぐす
脳科学の研究でも、ストーリーテリングには複雑さを軽減する力があることがわかっています。
カリフォルニア大学アーバイン校のラリー・ケイヒルが1996年に行った実験では、感情に訴える動画と、情報だけを淡々と伝える動画とでは、脳の反応に大きな差が出ました。感情に訴える動画を見せた時は、特に「扁桃体」という感情に関わる部位が活発になり、そこから記憶形成を担う「海馬」へ信号が送られていました。つまり、ストーリーテリングは情報を長く記憶に残す助けになるのです。
特に「主人公」といった馴染みのある要素が出てくると、視聴者は自然と登場人物に自分を重ね合わせ、既存の知識と結びつけます。こうして複雑なテーマが、分かりやすいパターンに変わっていくのです。
「シンプルな言葉」は理解を助ける
分かりやすいコミュニケーションをするには、言葉をできるだけシンプルにすることも重要。難しい専門用語を避け、複雑な考えをかみ砕いて伝えれば、世代を問わず、より多くの人に届きます。
もちろん「分かりやすさ」の基準は人や状況によって変わりますが、理解を助ける方法はたくさんあります。パターンを活用する、簡単な言葉で伝えるほかにも、画像や音声、動画など別のメディアを加える——こうした工夫で情報はぐっとシンプルになります。
さて、複雑さを解消する方法は分かりましたが、「自分から誰かへ分かりやすく伝えたい」「実際に動画を作ってみたい」という時はどうすればよいのでしょうか?
その答えのひとつが、私たちの提供する「simpleshow video maker」です。オンラインで誰でも解説動画が作れるサービスで、どんなに複雑なテーマでもAIが専門用語を使わずに「共感できるストーリー」へ変換します。さらに画像やアニメーションで重要なキーワードを強調し、視聴者が情報を理解し、記憶しやすくします。
複雑な世の中を分かりやすくしたい。そう思っている方は、ぜひご活用ください!
